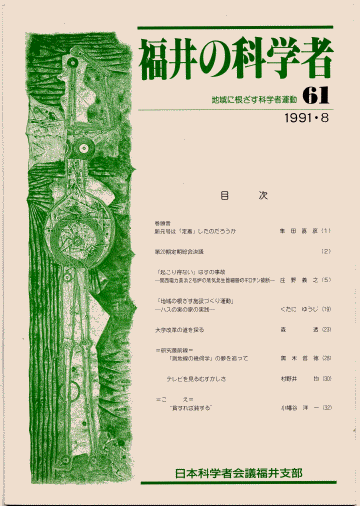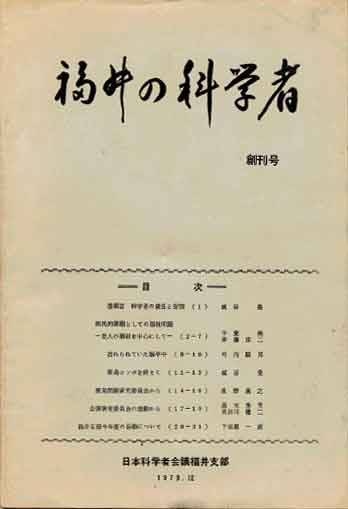第103号〜創刊号
第103号(2007.6.18)
| 「研究者の権利・地位宣言/倫理綱領」案にご意見を | |||
| 研究者の権利のための闘争 -NTT研究所でのたたかいをふりかえって- | |||
| 数学文化と数学教育についての再考 -エスノ数学に学ぶ-(中編) | |||
| 近代日本における科学技術体制(3) -国家総動員法と戦争のための科学・技術動員- | |||
第102号(2007.2.20)
| 「教育基本法の改悪を阻止し、憲法・教育基本法の精神をいかそう」 | 福井支部幹事会 | ||
| 「教育の国家統制を強める教育基本法「改正」案の廃案を求める」 | 日本科学者会議福井支部 福井大学教職員有志 | ||
追悼小特集 | 佐々治寛之先生の思い出 | ||
| 編集長としての佐々治先生 | |||
| 佐々治先生と福井県の昆虫目録 | |||
| 佐々治先生のおもいで | |||
| 佐々治先生と中池見湿地 | |||
| 佐々治先生安らかにお眠りください | |||
| | 福井県敦賀市中池見湿地保全の現状と課題 | 笹木智恵子 | |
| 近代日本における科学技術体制(2) -近代日本における科学の制度化- | |||
| =受贈誌= | | ||
第101号(2006.10.16)
| 日本国憲法と教育基本法の危機に思う | |||
| 構造改革が医療制度を破壊する | |||
| 働く人びととその家族の階層性からみた社会的自立の条件 -岐阜県X市Y町の住民生活実態調査から- | |||
| 福井豪雨による堤防決壊と足羽川ダム計画を考える | |||
| 数学文化と数学教育についての再考 -エスノ数学に学ぶ(前編)- | |||
| 近代日本における科学技術体制(1) -西洋の近代科学および技術の全面的導入- | |||
第102号(2007.2.20)
| 世界変革の先駆け-中南米 | |||
| 『福井の科学者』100号礼讃 | |||
| 私たちは今どこにいるか? -転換期における科学者の役割- | |||
| 『福井の科学者』100号に寄せて | |||
| 福井支部創設35年で『福井の科学者』が100号を越える | |||
| 『福井の科学者』100号おめでとうございます ~武蔵野通研分会創立40周年と『新しい風』~ | |||
| 「学力低下」論を超えたリテラシーの新たな構築 -PISA調査の提起などを受けて- | |||
| 中学校教員から見た「学力低下」の現状とその対策 ~理科教育ワークショップ研究会の取り組み~ | |||
| SSH研究と新課程における高等学校物理教育の現状 | |||
| 「知」は、どうしたら「物語」になるのか? ~殺伐とした「受験知」からの脱却~ | |||
| 大学で伸びる資質とは | |||
| ふたたび科学・技術に新しい風を ~16総学に思いをよせて~ | |||
| 稲木信夫著『すずこ記-詩人中野鈴子の青春-』 | |||
第99号(2006.2.20)
| 平和憲法の擁護と知識人の責務 | |||
| 教育基本法改正の動きをどうとらえるか | |||
| 私が九条を護らなければならないと考える理由 | |||
| ありのままの歴史を知り学びあうために 平和文化史料館ゆきのした」の資・史料の活用を | |||
| 自由民主党「新憲法法案」に反対する声明 | 第41期第2回幹事会 | ||
| 建築構造偽装事件と技術者倫理 | |||
| 西條敏美著『理科教育と科学史』大学教育出版 | |||
第98号(2005.10.20)
| 原子力発電と核兵器 | |||
| もんじゅ最高裁判決の問題点、再審請求と今後の運動 | |||
| 「もんじゅ」のそもそもから、ビデオ隠し事件まで | |||
| 原発問題を見直す | |||
| 日本科学者会議は原子力開発についてどう考えてきたか? ~支部例会での質問に答えて~ | |||
| 「第三のイタリア」にまちづくりを学ぶ -産地中小企業の元気の秘密を探る- | |||
| 医学者としての森鴎外(3) -医学者と文学者のはざまで- | |||
| 加藤武市氏が『畜産物と健康』出版 | |||
第98号(2005.10.20)
| 原子力発電と核兵器 | |||
| もんじゅ最高裁判決の問題点、再審請求と今後の運動 | |||
| 「もんじゅ」のそもそもから、ビデオ隠し事件まで | |||
| 原発問題を見直す | |||
| 日本科学者会議は原子力開発についてどう考えてきたか? ~支部例会での質問に答えて~ | |||
| 「第三のイタリア」にまちづくりを学ぶ -産地中小企業の元気の秘密を探る- | |||
| 医学者としての森鴎外(3) -医学者と文学者のはざまで- | |||
| 加藤武市氏が『畜産物と健康』出版 | |||
第97号(2005.6.10)
| 水素利用社会の光と影 | |||
| 福井県敦賀市中池見湿地の保全と「NPO法人中池見」 ‐市民・行政・企業のパートナーシップを求めて‐ | |||
| 希望ある明日をめざして ‐中池見検討協議会開催‐ | |||
| 中池身湿地の保全に関する公開質問状 | |||
| 中池見の保全に関する公開質問状の回答について | |||
| 中池身検討委員会委員の皆様 | |||
| 2004国際湿地シンポジウム中池見宣言 | in敦賀参加者一同 | ||
| 学校で教えたテレビ番組作りの力を地域でどう活用するか | |||
| 医学者としての森鴎外(2) ‐頑迷なる「秀才」が天下をとったとき‐ | |||
| 福井空港拡張反対運動別表 | |||
第96号(2005.1.26)
| 伊ケ崎暁生先生と科学者の権利問題 | |||
| 最近の学習心理学における動機づけの考え方 | |||
| 科学教育の啓発活動と高大連携 | |||
| 「ふくい思想の会」のこと ‐日本科学者会議福井支部結成の前史‐ | |||
| 鯖江市の合併問題と市民運動 | |||
| 医学者としての森鴎外 ‐むかし「脚気」という病気があった!‐ | |||
第96号(2005.1.26)
| 伊ケ崎暁生先生と科学者の権利問題 | |||
| 最近の学習心理学における動機づけの考え方 | |||
| 科学教育の啓発活動と高大連携 | |||
| 「ふくい思想の会」のこと ‐日本科学者会議福井支部結成の前史‐ | |||
| 鯖江市の合併問題と市民運動 | |||
| 医学者としての森鴎外 ‐むかし「脚気」という病気があった!‐ | |||
第95号 特集「福井のまちづくりを考える」(2004.12.24)
| 評価について考える | |||
| 福井のまちづくり ‐住民と商業者によるくらしの創造をめざして‐ | |||
| 福井のまちづくりの課題と展望 ‐まちづくりの主体になれる住民を育てる教育を‐ | |||
| 福井市における中心市街地活性化に向けて | |||
| 商人としてまちづくりを考える | |||
| チャレンジショップを経営して | |||
| 福井空港拡張反対運動の勝利的終結について | |||
第93・94合併号 特集「地域通貨」(2004.3.12)
| 日本近代史と朝鮮史 | |||
地域通貨の実践 | 地域通貨というメッセージ | ||
| 鯖江型地域通貨「しあわせ交換券ハピー」 | |||
| 地域通貨えちぜん「徳(トーク)」 | |||
| おばま地域通心券「マリン」 | |||
| 時間預託とナルクふくい | |||
地域通貨の批判的検討 | 地域通貨論解題 | ||
| 地域通貨の貨幣的考察 | |||
| 金融政策からみた地域通貨 | |||
| 地域通貨とモラル・エコノミー | |||
| 地域通貨と共同性 | |||
| 開発計画の中止と今後の課題 ‐敦賀市・中池見湿地保護活動経過報告‐ | |||
第92号 特集「自然エネルギーと環境問題」(2003.11.15)
| 地球的に考え地域的に行動すること | |||
| 雪国における太陽光発電普及の取組 | |||
| 石川県での再生可能エネルギー導入の現状と課題 | |||
| 自然エネルギー利用のあり方を考える | |||
| 熱サイホン式雪発電 | |||
| 自然熱による路面の雪対策 ‐蓄えられた太陽熱利用から蓄えての利用へ‐ | |||
| 夜叉ヶ池とその周辺部の生物多様性 ‐昆虫相を生物地理学・保全生物学観点から見る‐ | |||
第91号 特集「教育」(2003.7.15)
| 国立大学法人化問題を考える | |||
教育 | 学力問題再考 | ||
| 算数・数学科における総合的学習の実践例 | |||
| IPT活動のこれまでとこれから | |||
| 大学システムにおける多様性 | |||
| 福井医科大学医学科における新しいカリキュラム | 栗山勝・岡田謙一郎 | ||
| 日本海地域の大学 | |||
| 画期的な「もんじゅ」行政訴訟控訴審判決 | |||
| 在宅介護支援センターの役割と機能に関する実態調査報告(2) | |||
第90号 特集「食と農業」(2003.2.25)
| 再び「自立と共生」を考える | |||
| 健康長寿食を求めて20年 | |||
| 福井の食と文化 | |||
| 福井の食と農および健康 | |||
| 日本経済と農業 | |||
| 情報時代の農業 | |||
| 山本武著『一兵士の従軍記録』を編んで | |||
| 在宅介護支援センターの役割と機能に関する実態調査報告(1) | |||
第89号 自然エネルギー特集(2002.10.25)
| 諦めるのはまだ早い | |||
| 福井は自然エネルギー先進県になれるか | |||
| 福井県での木質バイオマス利用の試み | |||
| アフリカの未来と自然エネルギー | |||
| 自然エネルギーの未来 | |||
| 持続可能な社会・循環型社会・エネルギーに関するノート(Ⅰ) | |||
| 石油流出事故が海洋生物に及ぼす影響 | |||
| 出産に纏わる先人達の知恵から学ぶ科学の発展 | |||
| 在宅介護支援センターの役割と機能における政策・実践課題の批判的検討 | |||
第88号 福井支部結成30周年記念特集号(2002.6.25)
| 30年間の重みと変化 | |||
| 日本科学者会議福井支部の草創期について | |||
| JSA福井支部30周年記念講演会での報告 ‐九年間の活動日誌の紹介‐ | |||
シンポジウム | 21世紀の地域構造と公共交通のあり方 ‐主題と論点‐ | ||
| 公共交通機関のパラダイムシフトと今後の展望 ‐公共交通復権に向けて‐ | |||
| 人口構造の変化と地方公共交通のあり方 | |||
| 「暮らし方」から地域の足(公共交通)を見つめ直す | |||
| 公共交通機関の新しい姿に科学者からも発言を | |||
| 敦賀市中池見湿地保全活動の経緯 | |||
| 日本科学者会議との付き合い | |||
| 私の研究と原子力発電問題 | |||
第87号(2002.2.22)
| 福井空港拡張計画中止を歓迎しながら | |||
| 自主研究組織「空気砲グループ」の生い立ちから解散まで | |||
| 発掘された壺や甕などの考古学資料を電子化して利用するための研究 -考古学研究の支援をめざして- | 荻野繁春 | ||
| 畜産技術の現状と持続性のある畜産を構築するには 食肉の自給率と食糧安保-豚編- | |||
| BNL-E949実験に参加して -ニューヨーク州ロングアイランドでの実験生活- | |||
| 聖戦 -NHKニュースから見た日米文化- | |||
第86号(2001.10.26)
歴史の浅い日本の畜産-牛編- | |||
-教育に相応しい「情報化」の実現に向けて- | |||
| 「九・一八」事件と偽満州国に対する中国人の見方 | 訳審者 髙建斌 | ||
第85号(2001.6.1)
| 「満州国」について | |||
| デジタルとアナログを融合した学習環境を(2) -教育に相応しい「情報化」の実現に向けて- | |||
| GaN半導体の結晶欠陥評価 | |||
| 科学雑誌の変遷と社会 | |||
第84号(2001.2.13)
| 影山 剛先生ご逝去 | 児嶋眞平 | ||
| 「水脈」十年 | |||
| デジタルとアナログを融合した学習環境を(1) -教育に相応しい「情報化」の実現に向けて- | |||
| 地域に根ざす『福井の科学者』の存在価値 | |||
第83号(2000.9.25)
| カナダの学会で中池見湿地をアピール | |||
| 福井空港拡張計画の中止を求める | |||
| ゆきのした平和文化資料館のめざすもの | |||
| 空港拡張計画と反対運動の現局面 -2000年7月- | |||
| 遺伝子組み替え食品とは | |||
| 「福井の科学者」の刊行危機 | |||
第82号(2000.6.30)
| 大学は変わるか | |||
| 21世紀の大学像と独立行政法人化問題 | |||
| 日本の大学 -その現状・歴史的性格と改革の課題- | |||
| 訪問教育研究から「生活等援助制度調査」へ -教育から福祉への展開- | |||
| トンネル時間の評価の試み | |||
第81号(2000.3.28)
| 江戸の教育にも悖る国立大学の法人化策動 -国家百年の計は教育にあり- | |||
| 現行介護保険と介護保障の相違について -介護問題をどう捉えるか- | |||
| 在宅介護支援センターの予防的地域福祉機能 ~地域の社会資源としての機能と役割~ | 舟木紳介 | ||
| 地方財政の危機を考える | |||
| ノーマン・デンジンとの出会い -イリノイ大学研修から- | |||
| 最近の中国の変貌 | |||
| 西条敏美著『虹その文化と科学』恒星社厚生閣 | |||
第80号(1999.12.20)
| 「culture」と「文化」 | |||
| 絹ものがたり -その変遷を追って- | |||
| 大学生の基礎学力論議をどうとらえるか | |||
| 大学における競争原理と教育実践 | |||
| 新米議員奮戦記 | |||
| 情報公開の現状と課題について | |||
| 緊急声明 | 国立大学の独立行政法人化に反対し、 国民に開かれた大学をめざして | ||
| 編集後記 |
第79号(1999.9.18)
| 巻 頭 言 | 大学での歴史教育の現状 | ||
| 支 部 決 議 | 中池見湿地をフィールド・ミュージアムとして残そう | 第28回定期大会 | |
| 大学の自主性と民主主義を脅かす 「学校教育法等一部改正案」に反対する | |||
| 日本原電敦賀2号機一次冷却水大量漏れ事故の1か月 | |||
| 若狭湾沿岸原発事故の調査報告-そのⅡ | |||
| 二つの科学革命(2) -二十世紀科学革命と量子論の誕生- | |||
| 高木和美著『新しい看護・介護の視座』 看護の科学社 -看護・介護の本質からみた合理的看護職員構造の研究- | |||
| 編集後記 |
第78号(1999.6.15)
| 巻 頭 言 | 国旗・国歌の法制化小考 | ||
| 暖冬の科学論 -北陸は豪雪地帯ではない- | |||
| 戦国期の白山麓地域 | |||
| 都市祭礼と町並み -祭りを視野に入れたまちづくりに向けて- | |||
| 二つの科学革命(1) -十七世紀科学革命から死せる学問へ- | |||
| 編集後記 |
第77号(1999.3.10)
| 巻 頭 言 | 広末涼子は人寄せパンダか | ||
| 中国におけるボランテイア活動 -内蒙古における環境保全活動について- | |||
| ダイオキシンによる母乳・食品汚染人体影響 | |||
| 敦賀市中池見湿地の保全とフィールド・ミュージアム構想 | |||
| 地域防災を考える -神戸からの報告- | |||
| 足羽川ダム問題の経過と現状および今後の課題 | |||
| 中池見湿地保全に関する要望書 (福井県環境審議会に対する) | |||
| 編集後記 |
第76号(1998.12.14)
| 空港裁判から | |||
| 中池見湿地保全に関する申し入れ (大阪ガス株式会社に対する) | |||
| 中野鈴子に見る近代の結婚と女性 -家父長制と性支配を中心に- | |||
| 回想『野火』のころ -田中光子さんの研究リポートを聴いて- | |||
| 自治体職員の人事とキャリア形成 -福井県庁の事例より- | |||
| 研究最前線 | 沸騰現象の魅力 | ||
| 編集後記 |
第75号(1998.9.18)
| プルサーマル計画に明日はあるか? | 第27回定期大会 | ||
| プルサーマルに未来はあるか | |||
| 地震と設計 -阪神淡路大震災の3年から何を学ぶか- | |||
| エイズの話 -HIVの遺伝子を中心として- | |||
| 神奈川県立外語短大で何が起きたか | |||
| 佐々治 寛之著『テントウムシの自然史』 |
第74号(1998.3.30)
| 生涯学習と大学 | |||
-中池見湿地の保全とトラスト運動- | |||
| 基調講演 「21世紀の環境問題を展望する」 | |||
| シンポジウム 「自然を守るとは」 | 河野 昭一, 今大地 晴美 | ||
| 中池見湿地保全運動の現状 | |||
| 高木秀男著『若造たちの物理学』 | |||
第73号(1996.3.16)
| 敦賀市中池見湿地の保全を強く求める | |||
| 環境リスク管理の経済学 -最近の研究状況と課題- | |||
| 原発の耐震性 見直さなくていいのか -原子力施設耐震安全検討会報告書批判- | |||
| 高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏出事故の問題点 -特に連絡遅れとビデオ隠しについて- | 林 庄司 | ||
| 95年北陸地方自治研究集会・福井集会の報告 | |||
| 研究最前線 | 医用画像から電子ビームへ | ||
| 『光の探求史』 |
第72号(1995.7.31)
| 断層と地震 | |||
| 再考! 福井の地震 -過去・現在・未来- | |||
| 「阪神大震災の体験から」 | |||
| 足羽川ダム構想の“まやかし”と危険性 | |||
| 特 集 | 「福井の科学者」編集委員会 | ||
| (再録) 化学物質の環境中挙動と処理技術 -福井の科学者 No.62(1991年12月)より- | |||
| 河口先生の研究業績を顧みて | |||
| 追悼の言葉 | 影山 剛 嶋田 正 滝 史郎 首藤 重幸 小幡谷 洋一 隼田 嘉彦 佐々治 寛之 高木 秀男 伊藤 勇 |
第71号(1995.5.15)
| 戦後五十年、震災、そして科学について | |||
| 「私たちの戦後史」づくり運動 | |||
| 多様性尊重主義と自然保護 -選別主義的自然保護論批判- | |||
| 中池見の魅力と保全の意義 -ナツラリストの視点から- | |||
| 『科学者の権利と地位』日本科学者会議編 | |||
| 河口 英樹氏の死を悼む |
第70号(1994.12.20)
| 敦賀市中池見湿地の保全を求める | |||
| 敦賀3・4号機増設問題の経緯 | 林 庄司 | ||
| -自然保護の立場から- 中池見湿原(敦賀市)の植物 | 福永 吉孝 明石 英章 | ||
| 情報ネットワークの現状 | |||
| 北陸地方自治研究集会の現状と課題 -北陸自治研究集会を終えて- | |||
| 敦賀市「中池見湿地」関連資料集 | |||
| 金崎 栄次郎著 「続福井の空港問題を考える」 |
第69号(1994.5.20)
| 敦賀3・4号機増設に反対する | |||
| 原発増設は住民投票で 条例制定と取り組んだ敦賀からの報告 | |||
| 若狭湾沿岸原発事故の調査報告とその検討 | |||
| 兄 三上 誠 | |||
| 日本の恐竜化石発掘 | |||
| 清水修二著 差別としての原子力 | |||
| 研究最前線 | 「転換期」の農村研究 |
第68号(1994.2.20)
| コメの部分自由化と日本の農業 | |||
| 子供の映像理解と社会的サポート | |||
| 環日本海国際学術交流セミナーに参加して | |||
| もんじゅ訴訟の現段階とプルトニウム | |||
| SSC計画の終焉 | |||
| 研究最前線 | 被服設計と人体計測 | ||
| 『坂東弘治博士追悼文集』に寄せて |
第67号(1993.12.20)
| 中国の大学改革 | |||
| 福井工大高木秀男助教授の屈せぬ闘いに賛辞を送り 一層の支援活動をすすめよう | 第22回定期大会 | ||
| 中池見湿地の保全をめぐって | |||
| 勝山高原開発(法恩寺山リゾート開発)の現状と課題 | |||
| ヨーロッパ核燃料施設調査報告(2) | |||
| 「子どもの悩み110番」の取組み | |||
| 研究最前線 | コンピュータグラフィクス -プラトンからマンデルブルーローまで- | ||
| 高木秀男「科学思想としての物理学」 | |||
| エイズ検査について | |||
| 科学者会議代表幹事 原善四郎氏を悼む | |||
| 小選挙区制導入に断固反対する決議 | 第22回定期大会 |
第66号(1993.5.10)
| 46歳を迎えた現憲法の下における日本 | |||
| 生物の多様性をめぐって -ありふれた普通種と絶滅危惧種- | |||
| 農薬の使用は,今後どうなるか・・・? | |||
| 樫曲湿地「中池見」について | |||
| ヨーロッパ核燃料施設調査報告 | |||
| 研究最前線 | クオーク姫たちの色香 -グルーオンたちの束縛から逃れて- | ||
| 教育・福祉の行財政 | |||
第65号(1993.2.10)
| 存亡の危機に立つ「ゆきのした文化協会」 -いま自主的文化運動の灯を消してもよいのか- | |||
| 基調報告 | |||
| 共同ゼミナール「学習過程研究」の取組み | |||
| 受験体制と授業 | |||
| 中学校社会科の実践 | |||
| 中退者追跡調査から中学・高校教育に提言する | |||
| シンポジウムと若干の所感 | |||
| 討論のまとめ | |||
| 参加者の感想・その他 | |||
第64号(1992.9.1)
| 高木助教授の闘いとわれわれの今後の課題 | |||
| いま,福井の原発20年を問う -市民公開講座から- | |||
| 美浜原発の二十年と今日の美浜町 | |||
| 原子力発電と私達のくらしについて思う事 | |||
| 私にとっての原発 | |||
| 「まちづくり」についての福井市民の意識調査 | 桜井 康宏 | ||
| 研究最前線 | 最前線は最低線? | ||
| リボザイム -触媒活性のあるRNA |
第63号(1992.5)
| 大学の「教官」とその「責務」 | |||
| 大野の地下水問題 | |||
| 次世紀にもおいしく安価な水道を!! いま福井の水、まずくて高くなろうとしている?! | |||
| 福井県丹南地域における小河川扇状地間を 流れる地下水汚染について | 奥村 充司 | ||
| 研究最前線 | 唐代の均田法は空文法規であったか | ||
| カオスの話 -機械力学にもまだロマンがある- |
第63号(1992.5)
| 大学の「教官」とその「責務」 | |||
| 大野の地下水問題 | |||
| 次世紀にもおいしく安価な水道を!! いま福井の水、まずくて高くなろうとしている?! | |||
| 福井県丹南地域における小河川扇状地間を 流れる地下水汚染について | 奥村 充司 | ||
| 研究最前線 | 唐代の均田法は空文法規であったか | ||
| カオスの話 -機械力学にもまだロマンがある- |
第62号(1991.12.20)
| 私的疑似体験ニ題 | ||||
| 「子どもの権利条約」と学校生活 -苦悩する子どもの側から- | ||||
| 高校教育課程改革の方向について -91中教審答申の批判的検討- | ||||
| 「兼業稲作」からの脱却? -北陸の農業と農家について- | ||||
| 研究最前線 | 化学物質の環境中挙動と処理技術 | |||
| 日本中世「百姓」論をめぐって | ||||
| 編集後記 | ||||
第61号=還暦号(1991.8.12)
| 還暦を記念し装丁一新 1973年12月に創刊号を発刊して以来,本誌も今号で第61号となり,世間でいうところの『還暦』を迎えることとなった。刊行を支えて頂いた多くの執筆者と読者の皆さんに心より敬意を表したい。そして,これを機会に装丁を大幅に改訂することとした。表紙画は,本支部発行の単行本『地域を見直す』(10周年記念出版),『地域を考える』(15周年記念出版)と同じく三上誠氏によるものである。(O美術館『三上誠展-自己凝視から「宇宙」へ-』より)。 [編集後記冒頭の一節より] |
| 新元号は「定着」したのだろうか | |||
| 福井工大高木助教授の職場復帰の即時実現のために 今こそ全力をあげて支援運動を広げ強めよう! | 第20期総会 | ||
| 関西電力美浜2号炉の蒸気発生器細管破断事故にあたって | |||
| 「起こり得ない」はずの事故 -関西電力美浜2号炉の蒸気発生器細管のギロチン破断- | |||
| 「地域に根ざす施設づくり運動」 -ハスの実の家の実践- | |||
| 大学改革の道を探る | |||
| 研究最前線 | 「測地線の幾何学」の夢を追って | ||
| テレビを見るむずかしさ | |||
| “貧すれば鈍する” |
第60号(1991.2.25)
| 福井県自然環境保全3題を思う | |||
| 急増する子供のアレルギー -特に食物アレルギーについて- | |||
| 新聞研究ノート② 「『危ないお年寄り』探し」考 | |||
| 大学審議会は日本の大学の「保守性」を打破する“救世主”なのだろうか -森 透氏の所論にふれて- | |||
| 病める子どもに寄り添って -私の研究、私の方法- | |||
| 競合が作り出す多様な世界 | |||
| 美浜2号機の全てのデータを公開し安全確保の対策を |
第59号(1990.10.1)
| 「第14回県下原爆死没者追悼のつどい」へのメッセージ | |||
| 子どもの発達は脆弱か? | |||
| 普通高校の現場における若干の感想 | |||
| 障害者運動のゆくえ ⑥ -障害者運動は海を越えた- | |||
| 鄭7段は昭和生まれ? | |||
| 研究最前線 | 授業研究の新たな動向と課題 | ||
| 燃焼を解く -数値燃焼流体力学- | |||
| ある住民協定の問題 | |||
| 大学審議会の概要への雑感 |
第58号(1990.6.30)
| 決 議 | 「即位の礼」・大嘗祭に関する決議 | 第19回定期大会 | |
| 福井工大高木助教授の職場復帰の早期実現のために 今こそ全力を挙げて支援活動を広げ強めよう! | |||
| 野鳥の保護を訴える | |||
| 医療における情報化 -「豊かな国」の医療のシステムと医療情報システム- | |||
| 生命科学の新展開と大学 | |||
| 変曲点を過ぎたかどうか |
第57号(1990.3.1)
| 坂東さんを偲んで -坂東さんが福井に残したもの- | |||
| 再び大学の一般教育を考える | |||
| 情報専門学科におけるカリキュラム | |||
| 中世の越前金津宿 | |||
| 資産課税の制度と課題 | |||
| 「生涯教育」雑感 | |||
| 病名告知について |
第56号(1989.10.1)
| お釈迦を出さぬために | |||
| 反核・平和運動と「新しい思考」 | |||
| 福井県内の原発の事故・故障の最近の特徴 | |||
| 新学習指導要領を考える | |||
| 生活科の狙いは何か | |||
| 「頭の良くない」裁判官 | |||
| 原子力防災訓練見学記 |
第55号(1989.6.1)
| 解釈から変革へ -今,問われる科学者の力量- | |||
| 障害者運動のゆくえ⑤ -ベトナムの二重体児の発達を考える- | |||
| 地元新聞雑考・ノート | |||
| 斎藤公子の保育論に学ぶ(鷹巣ひかり保育園の基本設計をとおして) -計画論ノート・その6- | |||
| 日本血液事情 | |||
| 大学教員としての雑感 |
第54号(1989.3.1)
| 科学者の風景 | |||
| 大学教員の研究権と学問の自由 四天王寺国際仏教大学事件に関連して | |||
| 保育行政と保育料問題 -保育料はなぜ高いか- | 自治体問題研究会 | ||
| 原発問題の法的研究 原発における法的問題の概観 | |||
| 障害者運動のゆくえ④ -ベトナムの二重体児、ベトトドクの発達を願う会 | |||
| 一寸一言 | |||
| 天皇制と元号 |
第53号(1988.9.30)
| 「第12回県下原爆死没者追悼のつどい」へのメッセージ | |||
| バイオテクノロジーの展開 | |||
| 保健の授業づくり | |||
| 福井ならではの雪対策技術の開発を | |||
| 資 料 | 最近の学術体制をめぐる動き |
第52号(1988.6.1)
| 臨教審関連6法案の成立を許さず、国民合意の教育改革をめざそう! | 第17回定期大会 | ||
| 和解による一審勝訴判決の確定をふまえ、福井工大高木助教授の完全原職復帰をめざして闘いを続けよう | |||
| 「ハスに実の家」 -創立に至るまでと、これから- | |||
| 共に学び、共に生きるハスの実の会 -その歩みと今後の課題- | |||
| 「ハスの実の家」の新施設について -その概要と構想の過程- | |||
| 障害者運動のゆくえ③ -結合双生児に愛の車いすを- | |||
第51号(1988.4.20)
| 巻 頭 言 | 「自然に立つ」 | ||
| 障害者運動のゆくえ② -結合双生児に愛の車いすを- | |||
| 一乗谷朝倉遺跡の発掘調査について | |||
| 福井県における考古学の背景 | |||
| 中世の越前ろくろ師について |
第50号(1987.10.31)
| 再び「科学者の責任と役割」 | |||
保 育 | 共同保育所づくり運動をめぐって | ||
| ゆきんこ共同保育所の役割と今後の活動について | |||
| ゆきんこ新園舎建設運動のあゆみ | |||
| 大飯3・4号機増設と若狭湾既設原発に関する 住民自主ヒアリングの意見・質問について | 福井県民会議 |
第49号(1987.7.1)
福井工大高木助教授不当解雇裁判特集
| 学問思想の自由と科学者の権利を守るために福井工大高木助教授の現職復帰を実現するまで闘い抜こう | 第16回定期大会 | |
| 福井工大事件第一審判決について | ||
| 高木氏勝利判決によせて | 田島 薫 影山 剛 城谷 豊 坂東 宏治 | |
| 福井工大高木助教授不当解雇事件裁判資料 | (14) |
第48号(1987.4.1)
| 「名古屋大学平和憲章」の制定に思う | |||
| 障害者運動のゆくえ -結合双生児に愛の車いすを- | |||
| 高齢化社会における地域医療 | |||
| 「発達と教育」論に学ぶ -計画論ノート・その5- |
第47号(1987.3.31)
| 巻 頭 言 | 無題 | ||
| 15年戦争と福井空襲 | |||
| 小さな平和教育 | |||
| 自治体問題④ 地方自治体におけるコンピュータ利用(OAシステムの導入) | 自治体問題研究会 |
第46号(1986.9.30)
| 決 議 | 福井工大高木秀男助教授の不当解雇撤回裁判闘争を支援し 学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを発展させよう | 第15回定期大会 | |
| ソ連チェルノブイリ原子力発電所の大事故について | |||
| 越前国南条郡嶋村,丹生郡金谷,敦賀郡鋳物師村の鋳物師 | |||
| 「生活の社会化」論に学ぶ -計画論ノート・その4- | |||
| 自治体問題③ 地方自治体におけるコンピュータ利用(OAシステムの導入) | 自治体問題研究会 |
第45号(1986.3.15)
| 巻 頭 言 | 「国家機密法案」の再提出に反対し,その断念を要求する声明 | 福井支部 | |
| 福井県の、マツ枯れについて | |||
| 自治体問題① 職場運営における問題と提言 | 自治体問題研究会 | ||
| 富山県呉東地方の農家住宅(呉東Ⅰ型) -富山県の農家住宅・1- |
第44号(1985.11.30)
| 国家機密法の制定に反対する | |||
| ハスの実の家の実践の蓄積と課題 | |||
| ハスの実の家の生活と生活空間を見直す | |||
| 越前国五分一の鋳物師 |
第43号(1985.7.30)
| 福井工大高木秀男助教授の不当解雇撤回裁判闘争を支援し 学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを発展させよう | 第14回定期大会 | ||
| 自治体問題-① 福井における民間委託の問題 | 自治体問題研究会 | ||
| 井尻正二の科学論に学ぶ(下) -計画論ノート・その2- | |||
| シリーズ | |||
| 越前II型の古民家 木下家住宅について | |||
第42号(1985.6.15)
| 福井市議会での「国旗掲揚と国歌斉唱の励行を求める決議」採択に思う | |||
| ニホンカモシカの社会・行政科学的諸問題 | |||
| ハスの実の家の法人化(新しい施設づくり)運動の経緯と問題点 | |||
| 少年前期をどう考えるべきか ‐福大公開講座を受講して考えてみた事- | |||
| 井尻正二の科学論に学ぶ(上) -計画論ノート・その2- |
第41号(1985.2.28)
| 巻 頭 言 | 無題 | ||
| 見田石介・井尻正二・工藤晃の資本論の方法に学ぶ -計画論ノートその1- | |||
| 母親が選んだ算数教科書(その2) | 読みくらべる会 | ||
| “福井名産?プルトニウム”の行く方 |
第40号(1984.11.15)
| 福井工大高木秀男助教授の不当解雇撤回裁判闘争を支援し 学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを発展させよう | |||
| 「臨時教育審議会設置法案」の撤回を求める決議 | |||
| 福井臨工への核燃料工場誘致計画についての見解 | |||
| 福井臨工への核燃料工場誘致についての公開質問書 | |||
| シリーズ | |||
| 奥越・和泉村の住宅(越前Ⅳ型住宅)-福井の住宅(9) | |||
| 資 料 | 大飯発電所3・4号機環境影響調査書に対する質問書 | 反対する 福井県民会議 | |
第39号(1984.5.15)
| いま私学に問われているもの | |||
| イギリスにおける都市農村計画法と事前手続き(2) | |||
| 母親が選んだ算数教科書(その1) 1年生 | 読みくらべる会 | ||
| 同一性地位面接による自我同一性研究の展望 |
第38号(1984.1.31)
| 教養審答申をどう批判するか | |||
| 福井工大事件にかんする学問・思想の自由委員会の見解を読んで | |||
| 遊びを通して子どもを知る -4年生の教室から- | |||
| 大学入試と大学・高校教育 -最近感じていること- | |||
| シ リ ー ズ | |||
| 北越地方の住宅(越前Ⅲ型住宅) -福井の住宅(8) | |||
第37号(1983.10.31)
| 10月21日と10月12日 | |||
| 非行とその周辺 -この一年間に学んだ事- | |||
| 算数教科書を読み比べてわかったこと -県定教科書の被害者は子供達です- | 読みくらべる会 | ||
| 越前国芝原の鋳物師yy | |||
| 南越地方の住宅(越前Ⅰ型住宅) -福井の住宅(7) | |||
第36号(1983.7.30)
| 福井工大高木秀男助教授の不当解雇撤回裁判闘争を支援し, 学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを発展させよう | 第12回定期大会 | ||
| 日本学術会議法の改悪に反対し自主改革を尊重することを求める決議 | |||
| 若狭国遠敷金屋の鋳物師 | |||
| イギリスにおける都市農村計画法と事前手続(1) | |||
| 大学における教育 -福井大学工学部における一つの現実- | |||
| 社会問題としての非行(5) | |||
| シリーズ | |||
| 福井平野における現代農村住宅 -福井の住宅(6) | |||
第35号(1983.4.30)
| 原発の規制・監視機関の確立を | |||
| シリーズ | |||
| 福井県地域福祉問題研究会発足前後の記録 | |||
| 石炭火力における環境問題 | |||
| 農家住宅における接客・格式空間 -福井の住宅(5) | |||
| 「共通一次と大学教育」のシンポジウムを終えて | |||
第34号(1983.1.31)
| いまだ遠い「地方の時代」 | |||
| 「落ちこぼれ」と非行 | |||
| 社会問題としての非行(4) | |||
| 自然界における非対称性 | 4enter>沖 久也 | ||
| 越前平野における伝統的農家住宅の変容 -福井の住宅(4) | |||
第33号(1982.10.25)
| お城の石垣 | 11 | ||
| 特 集 | |||
| 福井県における原子力発電所の運転状況 | |||
| 若狭湾沿岸の原発の事故・故障 | |||
| 高速増殖炉「もんじゅ」の問題点 | |||
| 高速増殖炉と核燃料サイクル | |||
| 越前平野の伝統的農家 -福井の住宅(3) | |||
| 社会問題としての非行(3) | |||
第32号(1982.7.25)
| | 福井工大高木秀男助教授の不当解雇撤回裁判を勝利させ、学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを発展させよう | 定期大会 | |
| | |||
| 今子どもたちは -自立心を子どもに- | |||
| 社会問題としての非行(2) | |||
| 教科書裁判最高裁判決に寄せて | |||
| シリーズ | | ||
| 福井の農家 -その原型と生活- 福井の住宅(2) | |||
| | 第1回世界ベテラン卓球選手権大会の思い出 -国際交流と日本の卓球- | ||
| | 日本科学者会議福井支部10周年記念出版の編集進む | ||
第31号(1982.4.24)
| 研究創造活動における民主主義 | |||
| 福井の住宅規模 -福井の住宅(1)- | |||
| 社会問題としての非行(1) | |||
| 「スス」の話 | |||
| 福井の雪の特質 ‐雪害に関連して- | |||
| 五六豪雪と交通 | |||
第30号(1981.11.28):支部結成10周年記念特大号
| 巻 頭 詩 | あれから十年 | ||
| 日本科学者会議福井支部10年の歩み | |||
| 公害問題研究委員会の活動をふりかえって | |||
| 原発問題を考えて10年 | |||
| 農業・食糧問題研究委員会の歩み | |||
| 定期刊行物「福井の科学者」 | |||
| 支部活動に現れた「教育」10年 | |||
| JSA福井支部福井高専分会の歩み | |||
| 「原子力問題を考える会」の活動 | 庄野 義之 | ||
| NGOシンポジウムと日本科学者会議福井支部の活動 | |||
| 原発との出会い(覚え書きノート) | |||
| 日本科学者会議福井支部活動記録 | |||
第29号(1981.7.25)
| 日本原電敦賀発電所の事故についての声明 | |||
| 福井工大の高木秀男氏を支援し,その不当な解雇を撤回させ, 学問思想の自由と科学者の権利を守る闘いを強化するためのアピール | |||
| 福井工業大学高木秀男助教授の解雇撤回, 正当な地位回復の闘いを支持する声明 | 福井大学教職員組合 福井県高等学校京職員組合 北陸高等学校京職員組合 福井県民間教育研究団体連絡協議会 ゆきのした文化協会 福井工業高等専門学校教職員組合 高木秀男氏を支援する会 | ||
| 安全技術から見た原発の事故 | |||
| 公正な調査と原発誘致姿勢の転換を -敦賀原発の事故を振り返って- | |||
| 専門教科(農業土木科)における数学の応用について | |||
| 勧奨年齢の男女差別について |
第28号(1981.4.20)
| 早教育をめぐって | |||
| 家族安定化と女性解放 | |||
| 現代の子どもと児童文化 その2 | |||
| “公募制”による郷土の劇づくり運動 | |||
| 小学校の歴史教科書を見て感じたこと | |||
| 仏西旅行断片 (4)yy |
第27号(1981.1.25)
| 国際障害者年 | |||
| 学問の自由と科学者の責任ということについて | |||
| 福井支部結成9周年記念講演会 石谷清幹教授講演「エネルギーじきゅうの基本問題」の報告 | |||
| 仏西旅行断片 (3) | |||
| 私の秘蔵本-その3- 「戦旗」 | |||
| 若狭の原発最近の動きから | |||
| 住民公開ヒアリング意見・質問書 | 福井県民会議 |
第26号(1980.10.15)
| 「原水爆禁止を訴える統一福井県民会議」へのメッセージ | |||
| 現代の子どもと児童文化 その1 | |||
| 教師が語るとき | |||
| 仏西旅行断片 (2) | |||
| “スリーマイル”から1年 -若狭の原発で何が起こったか- (下) |
第25号(1980.7.15)
| アピール | 福井工大助教授高木秀男氏を支援し,学問思想の自由と 日本の教育・研究を守る闘いを発展させよう | 第9回定期大会 | |
| “「行幸目録」”と“みどりのデータ・バンク” | |||
| シリーズ | |||
| 福井市における地域施設の整備過程(戦後) -年表と解説- | |||
| 児童・生徒の姿勢について | |||
| 仏西旅行断片(1) | |||
| “スリーマイル”から1年 -若狭の原発で何が起こったか-(上) | |||
第24号(1980.4.15)
| アピール | 福井工大助教授高木秀男氏を支援し,学問思想の自由と 日本の教育・研究を守る闘いを発展させよう | 第9回定期大会 | |
| “「行幸目録」”と“みどりのデータ・バンク” | |||
| シリーズ | |||
| 福井市における地域施設の整備過程(戦後) -年表と解説- | |||
| 児童・生徒の姿勢について | |||
| 仏西旅行断片(1) | |||
| “スリーマイル”から1年 -若狭の原発で何が起こったか-(上) | |||
第23号(1980.1.15)
| 巻 頭 言 | 「物分りが悪い」ことのすすめ | ||
| 教員養成カリキュラムについて一つ思うこと -日教組大学問題検討委員会・最終報告を読んで- | |||
| ブラジル寸見 | |||
| 改訂高等学校学習指導要領について | |||
| 会員訪問・・・・新貝 鉚蔵氏の巻 | |||
| 「図書館作り」運動の意味するもの -「札幌の図書館づくりをすすめる会」に学ぶ- | |||
| 国際児童年と子どもの現状 |
第22号(1979.10.17)
| 法治主義ということ | |||
| 地域と図書館活動 -図書館における児童・障害者サークルへのサービスについて- | |||
| 地方文化づくりをめぐるノート | |||
| 新指導要領の実施にあたって思うこと | |||
| 大飯発電所の「安全解析」についての検討の記録 |
第21号(1979.7.30)
| スリーマイル島原子力発電所の事故と わが国の原子力開発についての決議 | 定期大会 | ||
| 高校入試改善案の批判と改革の展望 | |||
| 教育財政研究の一視点 | |||
| 子どもの権利と発達心理学 | |||
| 福井大学の総合大学化をめざして | |||
| 元号法と民主主義 | |||
| 私の秘蔵本 その1 |
第20号(1979.4.20)
| 「福井の科学者」のさらなる発展を | |||
大学入試 共通一次 | |||
| -共通一次試験をめぐって- | |||
| (1)高校進路指導からみた「共通一次」 | |||
| (2)ざわめいた学校―「共通一次」元年― | |||
| (3)「共通」は何をもたらしているか-高校現場からの一つの報告- | |||
| 福井児童文化運動論(5) -伝承遊び論を中心に- | |||
第19号(1979.1.20)
| 巻 頭 言 | 年頭雑感 | ||
| 地震の予知と防災 -福井地震30年目をむかえて- | |||
| 大学における一般教育科目についての雑談 | |||
| 中国見聞記 | |||
-支部例会の三氏の問題提起から- | |||
| 埋蔵エネルギー資源 | |||
| 太陽エネルギー -その特質と利用- | |||
| 原子力エネルギー ----4つの話---- | |||
第18号(1978.10.20)
| 安全でない安全基準 | |||
| 数学とその教育・PartⅡ | |||
| シャボンダマ考 | |||
| 核兵器完全禁止を国連に要請する代表団に参加して | |||
| 健康生活とスポーツ(Ⅱ) -本学学生の健康に関する2,3の問題点 | 長谷川 健二 | ||
| 福井児童文化運動論(4) -運動の組織化論を中心に- | |||
第17号(1978.7.15)
| 原子力発電問題についての決議 | |||
| 第2回日本海シンポジウムを成功させよう | |||
の報告 | 一般教育課程のばあい | ||
| 高等教育機関の現状と地方大学 | |||
| 羅生門なんか恐くない | |||
解説 | 関西電力高浜発電所(3,4号炉)の 『環境影響調査書』の検討から |
第16号(1978.4.15)
| 巻 頭 言 | 発想の顛倒 | ||
| 大学の将来構想を考える視点 | |||
| 福井児童文化運動論(3) -親子映画運動を中心として- | |||
| 地場の産業と地域社会 -健闘する小。零細機業-(後編) | |||
| 解説 有機農業序論 | 研究委員会 | (25) | |
第15号(1978.1.15)
| 巻 頭 言 | 科学者とはなにかということ | ||
| 教育問題委員会(準)をめぐって | |||
| 地場の産業と地域社会 -健闘する小・零細機業(前編)- | |||
| 解説 農業の現状と問題点を考える -安全な食糧生産のために- | 研究委員会 | ||
| 福井児童文化運動論(2) -福井子どもまつりを中心として- | |||
第14号(1977.10.15)
| ある物理屋の独言 | |||
| 福井児童文化運動論(1)福井子ども劇場を中心として | |||
| 福井県における文化財保存運動の現状と課題 | |||
| 東大寺領越前国糞置庄について | |||
| 「高速増殖炉」とは(その6)-開発体制の問題- | |||
| 夏休みが終わって | |||
第13号(1977.7.15)
| 科学と地方文化に対する県民・市民の要求にこたえよう | 第6回定期大会 | ||
| シ リ ー ズ | |||
| 福井県における現存森林植生と自然環境保全について | |||
| シ リ ー ズ | |||
| 糞置庄遺跡の意義とその破壊 | |||
| 最近の原発問題から | |||
| 気体デトネーション | |||
| 「高速増殖炉」とは(その5) - その構造Ⅱ,および問題点のまとめ- | |||
第12号(1977.4.15)
| 公開講座を終えて | |||
| 大学の講義と学生の理解度に関する一考察 | |||
| 福井の自然環境とその保全 | |||
| 足羽山の自然 | |||
| 福井の原発を考える -福井を考える市民公開講座第3回より- | |||
| 「高速増殖炉」とは(その4)-その構造Ⅰ- | |||
第11号(1977.1.15)-福井支部結成5周年記念号-
| 福井支部結成5周年に寄せて | |||
| 一列ちがいの運命 | |||
| 地方における大学の役割 | |||
| 教育者と科学者 | |||
| 住宅規模の地方性 | |||
| 敦賀原子力発電所物語 | |||
| 解 説 | 「高速増殖炉」とは(その3)-プルトニウムの話- | ||
| 福井支部準備会覚え書き | |||
| 支部活動日誌 | |||
| 日本科学者会議福井支部創立五周年に際して |
第10号(1976.10.15)
| 福井の科学者10号によせて | |||
| 「古河アルミ風洞試験」に関する見解 | 福井支部 | ||
| 児童公園その今日的問題 -実態調査を終えて- | |||
| 足羽山を考える | |||
| 昇天の花 | |||
| 「福井の科学者」・UFO・町内会 | |||
| 文献の値うちと「福井の科学者」 | |||
| 岐路に立つ出版界と地方出版の問題 | |||
| 「福井の科学者」に期待する | |||
| 「高速増殖炉」とは(その2) |
第9号(1976.7.15)
| 苦と楽と | |||
| 数学とその教育をめぐって | |||
| 福井市民の自治意識 | |||
| 低温 | |||
| 若狭湾の原子力発電-その10年間から-Ⅱ | |||
| 「高速増殖炉」とは(その1)‐原理について- | |||
第8号(1976.4.15)
| 食糧危機と農業の展望 | |||
| 若狭湾の原子力発電-その10年間から- | |||
| 健康生活とスポーツ | |||
| 伝統工芸と福井 | |||
| 県庁舎移転問題からまちづくり運動へ | 福井支部 | ||
| 若狭湾沿岸における原子炉設置をめぐる 最近の動きについての見解 | 福井支部 | ||
第7号(1976.1.15)
| 原子力発電の10年とわれわれの課題 | |||
| 僻地の子供について思うこと | |||
| 福井の交通事情 | |||
| 教員の労働条件の改善に関する若干の考察 | |||
| 「古河アルミ」排ガス拡散風洞試験報告書に関する要望書 | |||
| 福井城跡と県庁舎移転問題 | 福井支部 | ||
第6号(1975.10.15)
| 科学を県民のものに | |||
| 教員養成から見た福井大学 -その役割と現況- | |||
| 福井の教育 -その現状についての一考察- | |||
| 現場教師の求めるもの | |||
| 地盤沈下と用水原単位についてのメモ若干 | |||
第5号(1975.7.15)
| 地方文化の正しい発展のために広範で多面的な活動を展開しよう | 定期大会 | ||
| 続発する原子力発電所の事故についての決議 | |||
| 福井県坂井郡三里浜一帯における大気汚染と植物被害 | |||
| 「古河アルミ」排ガス拡散風洞試験の問題点 | |||
| アルミニウム精錬とは | |||
| 福井市民のサークル活動実態 -余暇問題に関する施設計画学的検討- | 施設計画研究会 | ||
第4号(1975.4.10)
| 悪夢 | |||
| シ リ ー ズ | |||
| 福井の経済 -繊維を中心に- | |||
| 地域開発と地場産業 -繊維機器の生産と流通をめぐって- | |||
| 関電美浜原発・日本原電敦賀原発の事故年表 | 原発問題委員会 | ||
| 科学について | |||
| 古河アルミ風洞試験についての県への要望書 | |||
第3号(1974.11.20)
| 国民の自由と民主主義を守り研究・教育の荒廃を阻止し 科学者の社会的責任を果たそう | |||
| 住みよい街づくりを考える -障害者と街づくり運動から- | |||
| 試験・評価・授業についての一提案 | |||
| 児童生徒と大学生とは区別して考えるべき | |||
| 試験や評価を物神化するな | |||
| 壺の値段 | |||
| 新刊書紹介 | |||
第2号(1974.5)
| 巻 頭 言 | 農業と食糧問題 | ||
| 農業生産と地域分化 断片的思考 | |||
| 福井県の公害行政と開発行政 | |||
| 「環境権」によせて | |||
| 大学における一般教育の現状と問題点 -日教組全国教研集会雑感- |